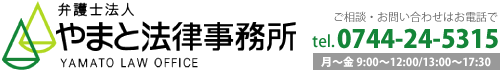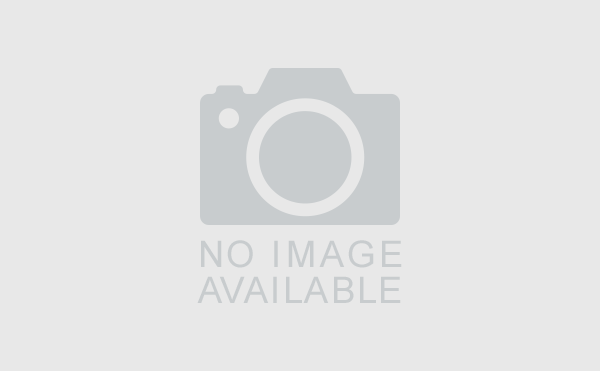「労働者の自立と連帯を求めて」を読んで (弁護士 兒玉修一)
最近、「労働者の権利」(日本労働弁護団)の書評欄において紹介されていた國武英生他編「労働者の自立と連帯を求めて~道幸哲也先生の教えと実践の軌跡~」(旬報社)を読みました。私も、今から30年前には、1年間、「道幸ゼミ」に所属しておりました(95年度)。この本を編集された門下生の皆さんからすれば、本当に末席も末席ではありますが。
本の中身は、当然、先生の論稿がメインとなっており、労働法を学ぶ意味(1章)に始まり、不当労働行為(3章)、ワークルール教育(5章)、労働委員会(6章)、労働法教育(7章)と多岐にわたっておりますが、その内容を私が正確に紹介することは、少し荷が重いです。是非、直接、読んでみてください。
むしろ、私が懐かしく思いましたのは、この本の中のそこかしこで顔を出している当時のゼミの様子に関するくだりです。
率直に述べて、当時、労働法はあまり人気がなく、学部生のゼミ希望者はわずか数名でした。これでは、ゼミとして成立しませんので、院生の皆さんにも加わっていただいておりました。院生の中には道内の企業に勤務する社会人もおられ、学部ゼミなのに、学年も、年齢も、出身地も、出身大学も、大学の在籍年数もバラバラという、少し変わった雰囲気がありました。
ゼミでは、毎週、労働法上の各論点に関連した判例3つくらいが取り上げられるのですが、学生には、この判例についての報告を毎回違うメンツ3人で作成してくるというミッションが課せられます。講義の空き時間に研究室に集まったり、夜中に大学の近所の喫茶店に集まったりして「あーでもない、こーでもない」と議論し、みんなの意見を調整し、レポートにまとめ、ゼミに挑むというのは、今から考えても、結構ハードでした。先生は「ゼミで1年間勉強をすれば、司法試験の労働法なんか余裕だろ?」とおっしゃっておられましたが、これはウソではありません。ただし、その「余波」で、刑法や商法は大変なことになりましたが。
また、本の中では、「ゼミのあと先生の研究室でみんなでお酒を飲む」という場面がたくさんでてきます。当時、大学構内のローン(芝生)のそこかしこでジンギスカンパーティ(通称「ジンパ」。お酒もラム肉もジンギスカン鍋も七輪も大学生協で準備できました)が開催されていましたので、特に不思議ではなかったのですが、とても牧歌的な気がします。今となっては、何を話していたのか、まるで覚えていないのですが、楽しかった思い出の一つです。
さて、弁護士登録して20数年経ち、労働者や労働組合の代理人はもちろん、企業の代理人もたくさん務めました。労働弁護士を標榜することはとてもできませんが、それでも平均的な弁護士よりは、労働法へのかかわりは深い方ではないかと思います。今後も、派手な活躍はできませんが、コツコツと取り組んでいきたいと考えています。