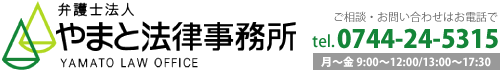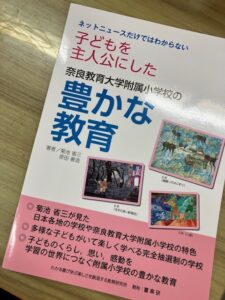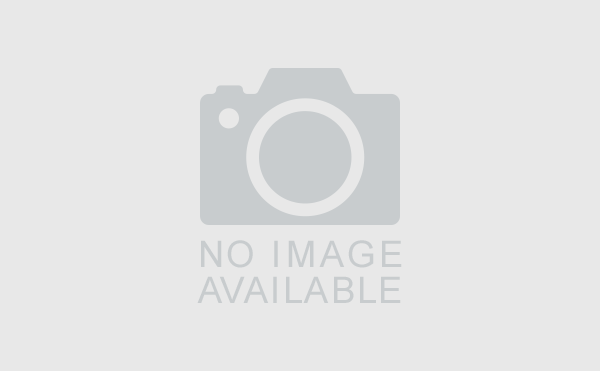SNSや掲示板サイトでの誹謗中傷に対する対応②(弁護士 松ケ下裕介)
1 はじめに
前回は、インターネット上の誹謗中傷に対する対応策の大まかな解説を行いました。
今回は、誹謗中傷に関する情報の削除のうち、削除請求の相手方や削除請求の要件等について、解説したいと思います。
2 誹謗中傷に関する情報の削除について
(1) 初動対応
誹謗中傷に関する情報を投稿され、その投稿を削除したいとき、まず、削除対象を把握するため、削除対象のURLの確認及び削除請求をする相手方(特に、サイト管理者)の特定が必要になります。
相手方の特定の具体的な調査方法としては、まず、ウェブサイトの一番下や上にある「会社概要」や「運営者情報」、「お問い合わせ」等から確認することが考えられます。
次に、上記の方法では、相手方が判明しない場合には、ウェブサイトのドメインから、WHOISサービスという検索システムを利用して、サイト管理者を検索する方法が考えられます。なお、ドメインとは、ウェブサイトのURLが「https://●●●.com」であれば、「●●●.com」部分をいいます。
以上の方法により、削除対象のURLの確認及び削除請求をする相手方の特定が初動対応として重要となります。
(2) 削除請求の相手方の選定について
次に、削除を求める相手としては、誰を相手とするかが問題となります。
相手方として、まず考えられるのは、書き込み等をした者(以下、「発信者」といいます。)です。
もっとも、発信者の特定が困難な場合や特定でき、訴訟を起こしたとしても、発信者に対し削除を直接強制できないのが現状です。
また、発信者が一度投稿すれば、発信者自身では削除できないようなウェブサイトも存在し、実効性がない場合もあります。
それに対し、ウェブサイトを運営する管理者やサーバの管理者については、削除する権限があり、実効性があります。また、裁判例上、「条理上の作為(削除)義務」という削除義務が認められる場合もあります。さらに、発信者が特定されている場合にも、管理者に対する請求が必ず否定されるわけではありません。
以上より、削除請求の相手方は、ウェブサイトを運営する管理者やサーバの管理者への請求が実効性のある方法といえそうです。
(3) 削除請求の法的根拠及び要件
削除請求の法的根拠については、前回のとおり、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)ではなく、裁判例や解釈上認められてきたものとしては、人格権に基づく妨害排除請求権としての差止め請求権があります。
同請求権の要件としては、人格権が違法に侵害されていること(違法性)であり、故意過失等の主観的要件は不要です。
もっとも、削除行為は、表現行為を抑制するものであることから、上記違法性の判断では、表現行為を行う利益との比較考量が行われます。
3 おわりに
以上が、削除請求の初動や削除請求の相手方の選定等についての解説でした。
誹謗中傷を内容とする情報が投稿されてしまった際、自身として、削除をしたいのか、それとも、発信者に責任追及まで求めたいのかを、時間的金銭的労力や見通し等を考慮した上で、検討する必要がありそうです。
また、前回も述べましたが、そもそも誹謗中傷の被害に遭わないため、安易に個人情報を他人に教えず、インターネット上にも載せないといった、事前の予防対策も重要です。
次回以降は、具体的な削除の方法や発信者への責任追及について解説していきたいと思います。